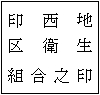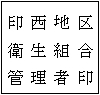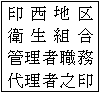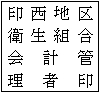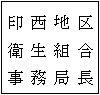○印西地区衛生組合処務規程
平成3年3月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、印西地区衛生組合の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について常時管理者に代わって決裁をすることをいう。
(3) 代決 事案について、管理者又は専決権者が不在のときに、その者に代わって、臨時に決裁をすることをいう。
(4) 不在 決裁をすることができる者に事故があり、又はその者が欠け、事案について決裁をすることができない状態をいう。
(5) 事務局 印西地区衛生組合組織条例(昭和51年条例第12号)第2条に規定する事務局をいう。
(6) 事務局長 印西地区衛生組合組織規則(昭和51年規則第1号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する事務局長をいう。
(7) 副参事 組織規則第4条第3項の規定により置いた印西地区衛生組合規則の規定の準用に関する規則(昭和59年規則第1号)第4条第1項に規定する副参事をいう。
(8) 事務局長補佐 組織規則第4条第2項に規定する事務局長補佐をいう。
(9) 係長 組織規則第4条第1項に規定する係長をいう。
(事務処理の原則)
第2条 事務の処理は、文書によることを原則とする。
2 文書は、丁寧に取扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が適正かつ迅速に行われるよう処理し、管理しなければならない。
(文書主任等)
第3条 事務局の文書に関する事務を処理するため、文書主任及び文書担当者を置く。
2 文書主任は、事務局長補佐又は係長の職にある者をもって充てる。
3 文書主任は、事務局長の命を受けて事務局における次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、交付、発送及び送達に関すること。
(2) 文書の整理及び保存に関すること。
(3) 文書の廃棄処分に関すること。
(4) 文書事務の改善指導に関すること。
4 文書担当者は、事務局長が指名する。
5 文書担当者は、文書主任の指示を受けて、その事務を補助するものとする。
(事務局長の責務)
第4条 事務局長は、事務局における文書事務の取扱いが第2条に規定する事務処理の原則に従って行われるよう指導しなければならない。
(文書の種類)
第5条 文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 令達文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 法第15条の規定により制定するもの
ウ 告示 管理者が法令の根拠に基づき、住民の権利義務に関係のある事項を公示するもの
エ 公告 管理者が不特定多数に周知させるため公示するもの
オ 訓令 事務局又は事務局長に対して指揮命令するもの
カ 指令 申請、出願等に対して機関の意思を示達するもの
(2) 往復文書 通達、通知、依頼、照会、回答、報告、協議、申請、進達、副申、諮問、答申、建議、出願、届出その他これらに類するもの
(3) その他の文書 任免等のため辞令、表彰状その他前各号に該当しないもの
(文書の記号及び番号)
第6条 施行する文書には、公告、任免等のための辞令、表彰状その他事務局長が指示した文書を除き、次の各号に掲げるところにより、記号及び番号を付さなければならない。
(1) 令達文書の記号は、印西地区衛生組合と表示したあとに令達種目を付して表示するものとする。
(2) 令達文書以外の文書の記号は、「印西衛」をもって表示するものとする。ただし、秘密を要する文書については、文書記号の次に「秘」の文字を追加するものとする。
(3) 文書の番号は、当該文書の記号ごとに会計年度により表示するものとする。ただし、条例、規則、告示及び訓令にあっては歴年により表示するものとする。
(4) 同一事件の文書については、同一の番号を用いることができる。この場合において、令達文書以外の文書のうち会計年度を超える同一事件の文書にあっては、文書記号の前に当該事件に係る当初の会計年度を表示するものとする。
(5) 同一種類の文書のうち事務局長が必要であると認める同一件名の文書については、あらかじめ、同一件名のものごとに一の番号を定め、当該番号ごとに枝番号を表示することができる。
(6) 前3号の規定にかかわらず、軽易な事件に関する文書については、文書番号を省略して号外とすることができる。
(文書等の収受)
第7条 事務局に到達した文書及び物品は、文書主任が次の各号に掲げるところにより収受しなければならない。
(1) 文書及び物品は、直ちに開封し、当該文書の余白に収受印を押印するとともに行政文書管理簿の所定欄に必要事項を記録の上、文書番号を付し、事務局長の閲覧を受けなければならない。ただし、指示等を要しない軽易な文書については、行政文書管理簿の記録を省略することができる。
(2) 親展文書は、開封しないで、封筒の余白に収受印を押印するとともに、管理者あてのものにあっては事務局長、その他の文書にあっては名あて人に配布するものとする。
(3) 刊行物、ポスターその他収受印を必要としない文書及び物品は、第1号の規定にかかわらず、収受印の押印を省略することができる。
2 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、取扱者の認印を押印しておかなければならない。
(文書の発信者名)
第8条 施行する文書の発信者名は、すべてその権限を有する者の名を用いなければならない。ただし、法令等の規定に定めがある場合又は文書の性質若しくは内容により特に必要がある場合は、組合名又は事務局長名を用いることができる。
2 前項の発信者名は、組合名を用いる場合を除き、職氏名を表示するものとする。ただし、その内容により氏名を省略することができる。
(公印)
第9条 公印の種類、ひな形、寸法、用途及び公印保管者は、別表第1のとおりとする。
(決裁の手続)
第10条 決裁に至るまでの手続は、決裁事項を所管する係長から順次上級の職にある者の回議を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において、他の係と協議又は調整する必要のある事案については、他の係に合議しなければならない。
3 前項の合議は、所管係長の回議を経た後に、他の係に合議するものとする。
(管理者の決裁事項)
第11条 管理者の決裁を要する事項は、おおむね別表第2のとおりとする。
(事務局長の専決事項)
第12条 事務局長が専決できる事項は、別表第3のとおりとする。
(管理者代決者)
第13条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
(会計管理者代決者)
第14条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指名する事務吏員は、会計管理者があらかじめ指定する事務について代決をすることができる。
(事務局長代決者)
第15条 事務局長が不在のときは、副参事がその事務を代決する。
2 前項の場合で副参事が不在のとき又は副参事を置いていないときは、事務局長補佐がその事務を代決する。
3 前項の場合で事務局長補佐が不在のとき又は置かれていないときは、事務局長があらかじめ指定する事務について、当該事務を所管する係長が代決することができる。
(代決の制限)
第16条 この訓令に定める代決事項であっても、特に重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は決裁権者があらかじめ指示した事項については、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので決裁権者の許可を得たものは、この限りでない。
(代決の処理)
第17条 代決した事項については、決裁権者が不在でなくなったとき、直ちにその後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項又はあらかじめ決裁権者の指示した事項については、この限りでない。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務等に関しては、栄町の関係規定を準用する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月26日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月4日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 用途 | 公印保管者 |
印西地区衛生組合之印 |
| 方24ミリメートル | 組合名をもって処理する文書 | 事務局長 |
印西地区衛生組合管理者印 |
| 方21ミリメートル | 管理者名をもって処理する文書 | 事務局長 |
印西地区衛生組合管理者職務代理者之印 |
| 方21ミリメートル | 管理者職務代理者名をもって処理する文書 | 事務局長 |
印西地区衛生組合会計管理者印 |
| 方21ミリメートル | 会計管理者名をもって処理する文書 | 会計管理者 |
印西地区衛生組合事務局長 |
| 方21ミリメートル | 事務局長名をもって処理する文書 | 事務局長 |
別表第2(第11条関係)
管理者の決裁を要する事項 |
(1) 組合行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更 (2) 組合議会の招集 (3) 条例案、予算案及びその他議案(認定、報告を含む。)の決定 (4) 権限の委任 (5) 職員の任免、服務、分限、懲戒及び給与の決定 (6) 特別職の職員及び付属機関の委員の任免 (7) 法第292条の規定により準用する同法第179条第1項に規定する専決処分の決定 (8) 訴訟及び不服の申し立て (9) 表彰及び儀式の決定 (10) 起債 (11) 規則及び訓令の制定及び改廃 (12) 重要な告示、指令、通達、通知、申請、届出、報告、照会及び回答 (13) 重要な許可、認可 (14) 組合の区域及び名称の変更 (15) 事務局長事務引継の報告 (16) 事務局長の出張命令及び復命並びに職員の県外出張の復命 (17) 事務局長の年次休暇及び特別休暇の承認並びに職員の職務専念義務の免除 (18) 事務局長の専決事項に属さない事項(前各号に定めるもののほか、異例若しくは疑義のある事項、新規な事項又は特に政策的な事項) |
別表第3(第12条関係)
1 文書等に関する事項
事務局長の専決事項 |
(1) 定例的な調査、報告及び進達 (2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答 (3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付 (4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認 (5) 公簿、公図等の閲覧の許可 (6) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令並びに特殊勤務命令 (7) 職員の出張命令及び復命(県外出張を除く。) (8) 職員の年次休暇及び特別休暇の承認 (9) 地積の分合筆 (10) 扶養親族の認定並びに通勤届及び住居届の受理 (11) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可 (12) 文書の収受及び発送 (13) 組合例規集の編集発行 (14) し尿処理施設の管理 (15) し尿処理施設の補修及び工事の監督 (16) 公害予防に関すること。 (17) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理 |
2 財務に関する事項
(単位:万円)
執行区分 | 事務局長の専決事項 | ||
歳入の調定及び通知 | 全額 | ||
歳出予算に基づく支出負担行為 | 1 報酬 | 全額 | |
2 給料 | 全額 | ||
3 職員手当等 | 全額 | ||
4 共済費 | 全額 | ||
5 災害補償費 | 全額 | ||
6 恩給及び退職年金 | 全額 | ||
7 報償費 | 300未満 | ||
8 旅費 | 全額 | ||
9 交際費 | 全額 | ||
10 需用費 | 燃料費 | 全額 | |
その他 | 300未満 | ||
11 役務費 | 300未満 | ||
12 委託料 | 300未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | 300未満 | ||
14 工事請負費 | 300未満 | ||
15 原材料費 | 300未満 | ||
16 公有財産購入費 | 80未満 | ||
17 備品購入費 | 80未満 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 50未満 | ||
19 扶助費 | 全額 | ||
20 貸付金 | 300未満 | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 専決なし | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | ||
23 投資及び出資金 | 300未満 | ||
24 積立金 | 全額 | ||
25 寄附金 | 専決なし | ||
26 公課費 | 全額 | ||
27 繰出金 | 全額 | ||
年度及び科目の更正 | 全額 | ||
歳入戻出 | 全額 | ||
歳出戻入並びに資金前渡及び概算払の精算 | 支出負担行為の専決区分に準じる。 | ||
振替収支命令 | 全額 | ||
歳入歳出外現金の受入及び払出 | 全額 | ||
予備費の充当 | 100未満 | ||
流用 | 100未満 | ||
支出命令 | 全額 | ||
備考
1 支出負担行為額を変更するときは、増額となる場合は変更後の額に、減額となる場合は変更前の額に該当する専決区分による。
2 継続費又は債務負担行為で当該年度における支出負担行為にあっては、当該年度の契約金額に該当する専決区分による。
3 契約に関する事項
執行区分 | 事務局長の専決事項 |
執行伺 | 財務に関する事項の支出負担行為の専決区分に準じる。 |
一般競争入札参加者の資格決定、資格審査の申請時期、方法等の公示及び公募による入札の公告 | 全件 |
入札の参加資格審査の結果通知及び指名競争入札の指名通知 | 全件 |
予定価格、最低制限価格、調査基準価格及び失格基準価格の決定 | 全件 |
異議申立ての回答書の作成及び通知 | 財務に関する事項の支出負担行為の専決区分に準じる。 |
随意契約による場合の予定価格調書及び見積書の開封 | 全件 |
契約締結伺 | 財務に関する事項の支出負担行為の専決区分に準じる。 |
部分払いの決定 | 全件 |
検査の報告 | 全件 |
監督職員を命ずること | 全件 |
検査職員を命ずること | 全件 |